チチェン・イツァ
2009/01/01
午前9時にホテルに迎えにきたガイドは、ちょっと体格が良くて陽気なルイス。10人のお客を車に乗せての2時間の旅できれいな遺跡のメインゲートに到着すると、ここでルイスはお客を待たせてしばしガイド仲間たちと談合を始めました。実はバスの中ですでに判明していたことですが、10人のお客のうち英語を使うのは私だけで、残りの9人は全員スペイン語。そこで(こういう場合の常道ですが)ルイスは現地でガイド仲間を見つけ、お客のシャッフルをしようとしていたのです。しかしどうやら適当なガイド仲間をつかまえることができなかったらしく、諦めたルイスはその後、9人のお客にスペイン語で説明した後、私1人のために同じ説明を英語で繰り返すことになってしまいました。当然その間、スペイン語のお客たちはてんでに写真をばしばし撮影することになります。

| Preclassic | 500 B.C. to 325 A.D. | オルメカの影響 | |
| Classic | Early Classic | 325 to 625 B.C. | マヤ独自の文化が発展 |
| Flowering | 625 to 800 A.D. | 最盛期 | |
| Decline | 800 to 925 A.D. | 都市の放棄 | |
| Transitional | 925 to 975 A.D. | 古典期以前のレベル | |
| Maya-Toltec | 975 to 1200 A.D. | 中央アメリカからの進出と都市同盟 | |
| Mexica Absorption | 1200 to 1540 A.D. | 同盟の崩壊と混乱 | |
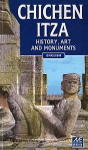 チチェン・イツァは新旧二つのエリアに別れており、南側の旧チチェンは古典期に築かれ、マヤ独自の文化の色彩が濃厚です。ここはいったん放棄され、その後10世紀にメキシコ中央高原のトルテカ文化と融合した文化の担い手が、旧チチェンの北側に新たな建造物群を築造しました。こちらが新チチェンと呼ばれるエリアで、さまざまな意匠にトルテカ色がはっきりと窺えます。ウシュマルと同盟を結んでユカタン半島北部に威勢を振るったのは、この新チチェンの方です。
チチェン・イツァは新旧二つのエリアに別れており、南側の旧チチェンは古典期に築かれ、マヤ独自の文化の色彩が濃厚です。ここはいったん放棄され、その後10世紀にメキシコ中央高原のトルテカ文化と融合した文化の担い手が、旧チチェンの北側に新たな建造物群を築造しました。こちらが新チチェンと呼ばれるエリアで、さまざまな意匠にトルテカ色がはっきりと窺えます。ウシュマルと同盟を結んでユカタン半島北部に威勢を振るったのは、この新チチェンの方です。
まずは、ゲートに近い新チチェンから見て回ります。
こちらが有名なエル・カスティージョ、またの名をククルカン神殿。冥界の9層を示す9段の基壇を持ち、高さは24m。内部に隠された古い神殿には赤いジャガー像が置かれ、その目に使われた翡翠はモタグア川流域(グアテマラ)からもたらされたものだそうです。ただし、残念ながら数年前に転落事故があったため、現在は階段を登ることも神殿内部を見ることも禁じられています。また、外面は東西南北に91段の階段を持っており、91段×4と最上部の神殿の1段を足して365日を示すほか、各面に9段が階段をはさんで二つあることから18段で、これはマヤ暦が20日を1単位とする18月と不吉な5日をもって1年を構成したことに対応しています。そして春分と秋分の日の午後3時には、地面に接するところにククルカン(ケツァルコアトルのマヤ名)の頭部を持つ北の階段の側面に9段のテラスが作る影がうねうねと波打って、あたかもククルカンがピラミッドの上から地上に降り立ったように見え、毎年その時期のこの遺跡周辺はお祭りになるのだそう。また、このピラミッドには視覚的効果だけでなく音響的な仕掛けもあって、階段に正対して手を叩くと周波数の高いククルカンの鳴き声(?)が返ってきます。ウシュマルの魔法使いのピラミッドの前や、パレンケの太陽の神殿と葉の十字架の神殿の間で手を叩いても同様の反響効果が得られますが、マヤ人の建築家の技巧にはほとほと感心するばかりです。

こちらはジャガーの神殿で、神殿の上に登るとその裏にある球戯場を見下ろすことができるようになっていますが、この階段の急勾配はちょっと怖いかも。また、写真では小さくてよくわかりませんが、上の四角い建物の基部から突き出しているのはククルカンの頭部です。
こちらが尋常ではない広さの球戯場の中で、7対7に分かれてゴムのボールを腕と足で打ち合い、壁から突き出ているリングに(通すのではなく)当てればそこで勝敗がつくというルールだったようです。リングの浮彫りはやはりククルカンで、王族しか見ないので客席は両端の貴賓席を含めごくわずか。そして見てのとおり壁がわずかに前傾しており、音がとてもよく響くようになっています。ここで選手達が声を上げながらボールを奪い合ったら、選手も観客もかなりヒートアップしたことでしょう。

球戯場の壁の浮彫りには、勝者が首を斬られて吹き出した7筋の血しぶきが蛇になって豊穣をもたらす図が描かれています。なんで勝者が?と怪訝な顔をするゲストたちに、ルイスは「当時は今とは価値観が違いますから。自分の命を神に捧げることは大変な名誉だったのです」と説明していました。

こちらは球戯場の近くにあるツォンパントリ(頭蓋骨陳列台)で、2007年に見た「インカ・マヤ・アステカ展」ではアステカが捕虜にしたスペイン人の頭部を串刺しにしてツォンパントリさらしたという話が紹介されていましたから、これはやはりメキシコ中央高原の習慣を反映したものです。

ジャガーと鷹の台座の壁面には人間の心臓をつかんだジャガーや鷹が浮彫りにされており、近くには金星の台座もあって、こうした台座は生贄の儀式に使われたようです。階段の両脇にククルカンの頭部が突き出していますが、これを見ながらのルイスと私の会話。「日本でも蛇はsacredでしょう?」「?」「白い蛇は崇められると聞いていますけど」「!」「それに亀は長寿のシンボル。マヤと日本は似た文化を持っているようですね」……なるほど、というかルイスはどこからそうした知識を仕入れたのだろう?


次に台座群から北へしばらく歩いて、直径60m、水面までの高距22m、水深20mとユカタン半島で最大級だというセノーテを見物しました。

カバーの記事で書いたように、セノーテは石灰岩の台地であるユカタン半島の地下水脈上が陥没してできたもの。川のないユカタン半島北部で貴重な水源となるだけでなく、ここチチェン・イツァのセノーテは信仰の対象ともなり、子供、処女、戦士といった人身御供や宝物などのさまざまな貢ぎ物が捧げられてきました。人身御供は、セノーテの縁辺に作られたスチームバスで身を清めてから捧げられたそうです。

セノーテから新チチェンに戻って今度は南の旧チチェンに向かいましたが、その道の途中にあるのがこの高僧の墳墓と呼ばれる建物です。ルイスの説明によればこれは本当の墓で、被葬者と17人の殉死体が内部から見つかっているということです。この見た目はエル・カスティージョを小型にしたような感じで、階段の下にはククルカンの頭がありましたから、旧チチェンにあってもこの建物自体はメキシコ中央高原の文化の影響を受けているようです。
こちらが旧チチェンを代表する建造物であるカラコル(天文台)。と言っても建造されたのは比較的新しく西暦900年から1000年の頃で、高さ9mのプラットフォームの上に13mの観測台が乗り、円筒状の壁に開けられたスリットから太陽や月、金星、プレアデス(Tzabと呼ばれました)を観測して、高度に正確な暦を作っていたそうです。ただ、残念なことにここも今は登ることができません。
カラコルの南にある巨大な尼僧院と、その近くの華麗な教会。いずれも名前は後世に勝手につけられたもので、実際の用途はわかりませんが、特に教会の方は典型的なプウク様式による装飾に覆われており、開口部の上のケツァル羽根飾りをつけて結跏趺坐する人物は支配者層、その左右のチャック像の額には太陽神が小さく乗っていて、全体としてもこの開口部が口となった大きな顔のように見えます。そしてここは、神々の国との結びつきをもたらす施設として作られていたようです。

新チチェンに戻って最後に巡り見たのが戦士の神殿です。その周囲に整然と立ち並ぶ膨大な数の石柱はメキシコ中央高原のトゥーラ遺跡との関係を示唆し、他のマヤ遺跡では見られないものです。また神殿本体の上の方には面白いことにチャックとククルカンが共存し、そして正面階段の上には神々と人との間をとりもつメッセンジャーであるチャクモールが2体のククルカンの柱の前に仰臥していました。かつては生贄の心臓を載せて血に染まりながら王の祝福を受けたであろうチャクモールも、今はさまざまな国からやってきた観光客たちを静かに見下ろしているだけで、どことなく物足りなさそうな風情です。
こうしてトルテカ文明の影響下に後古典期の北部マヤの覇権をウシュマルと共に担ったチチェン・イツァでしたが、13世紀に反乱が起こり、政治権力の中心は両都市の中間に新たに建設されたマヤパンに移ってチチェン・イツァは放棄されてしまいました。16世紀にスペイン人司教がチチェンの建造物群に関する記録を残していますが、その後はこの地は忘れられてジャングルに埋もれ、再び日の目を見るようになったのは1840年代になってからのことだそうです。

これで、この旅での遺跡探訪は全て終了です。14時15分にゲートを出てこの日も遅めの昼食をとった後、メリダへ戻る皆と別れて私はカンクンに向かう16時発のバスに乗るはずでしたが、うまい具合にルイスが知り合いのドライバーをつかまえてくれて、1時間早くチチェン・イツァを発つことができました。ルイス、ありがとう!
夕闇迫るカンクンに着いたのは17時50分で、すぐに現地エージェンシーに電話をしてホテルに来てもらい、ちょっとしたトラブル(料金が振り込まれていないと横柄に告げる受付のあんちゃんに対し現地エージェンシーのお姉さんはキレかけながら粘りの交渉)はあったものの無事チェックインできました。しかし、ようやく一息ついた頃には外は真っ暗で、せっかくのリゾート地カンクンも窓の外の波の音でその景観を想像することしかできませんでした。
